脆弱性診断のやり方が分かる!初心者でも自分でできる5つのステップを徹底解説
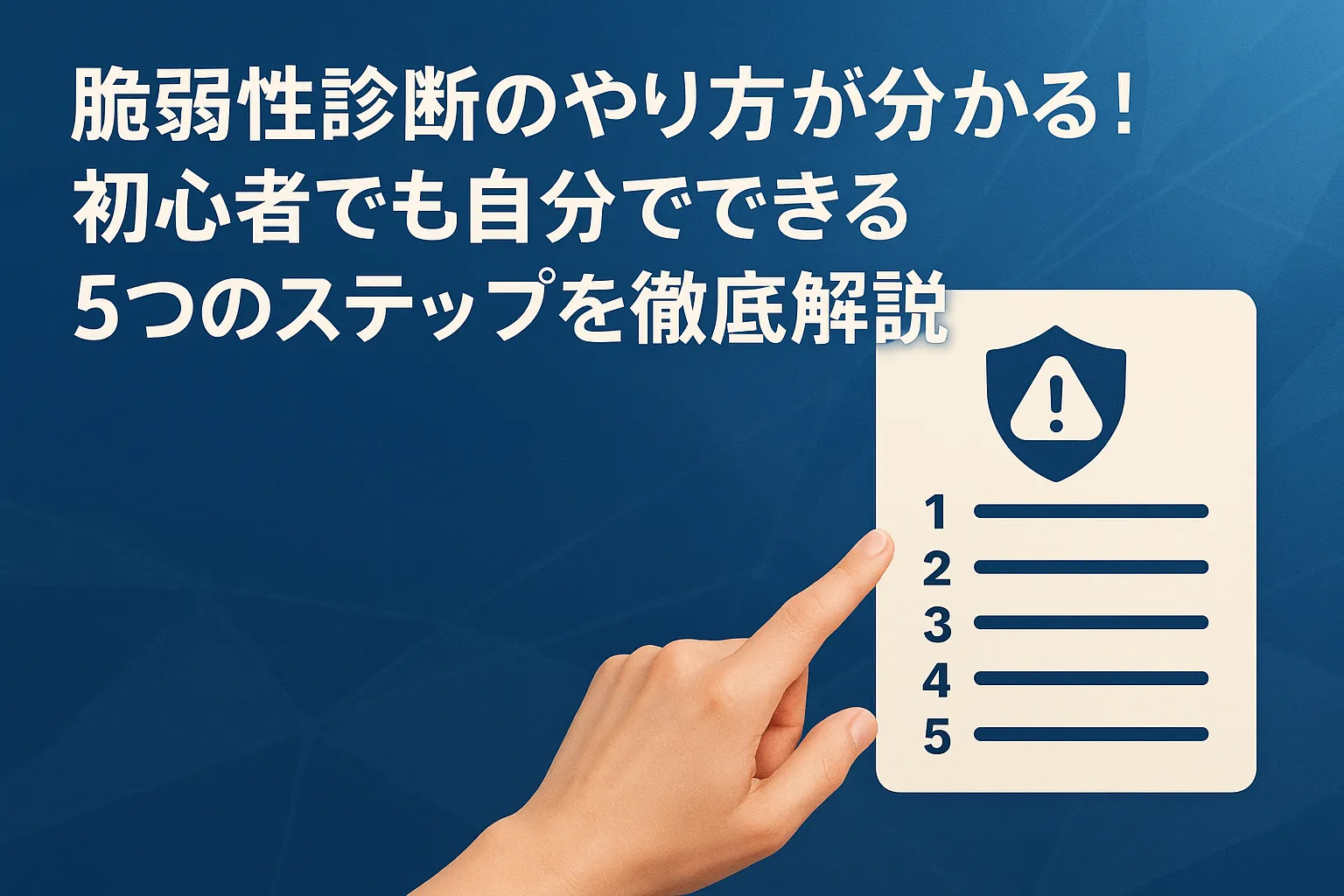
「自社のWebサイトのセキュリティは大丈夫だろうか?」
「最近よく聞く情報漏洩、うちのサイトは他人事じゃないかも…」
Webサイトの運営を担当していると、このような不安がよぎる瞬間はありませんか。
しかし、専門業者に脆弱性診断を依頼するのは費用も手間もかかり、何から手をつければ良いのかわからない、という方も多いはずです。
この記事では、そんなお悩みを持つWeb担当者のあなたのために、セキュリティ専門家でなくても自分でできる脆弱性診断のやり方を、5つの具体的なステップに沿って分かりやすく解説します。
この記事を読めば、漠然としたセキュリティへの不安を解消し、自社のWebサイトを安全に運営するための確かな第一歩を踏み出すことができます。
そもそも脆弱性診断とは?目的と必要性をサクッと理解
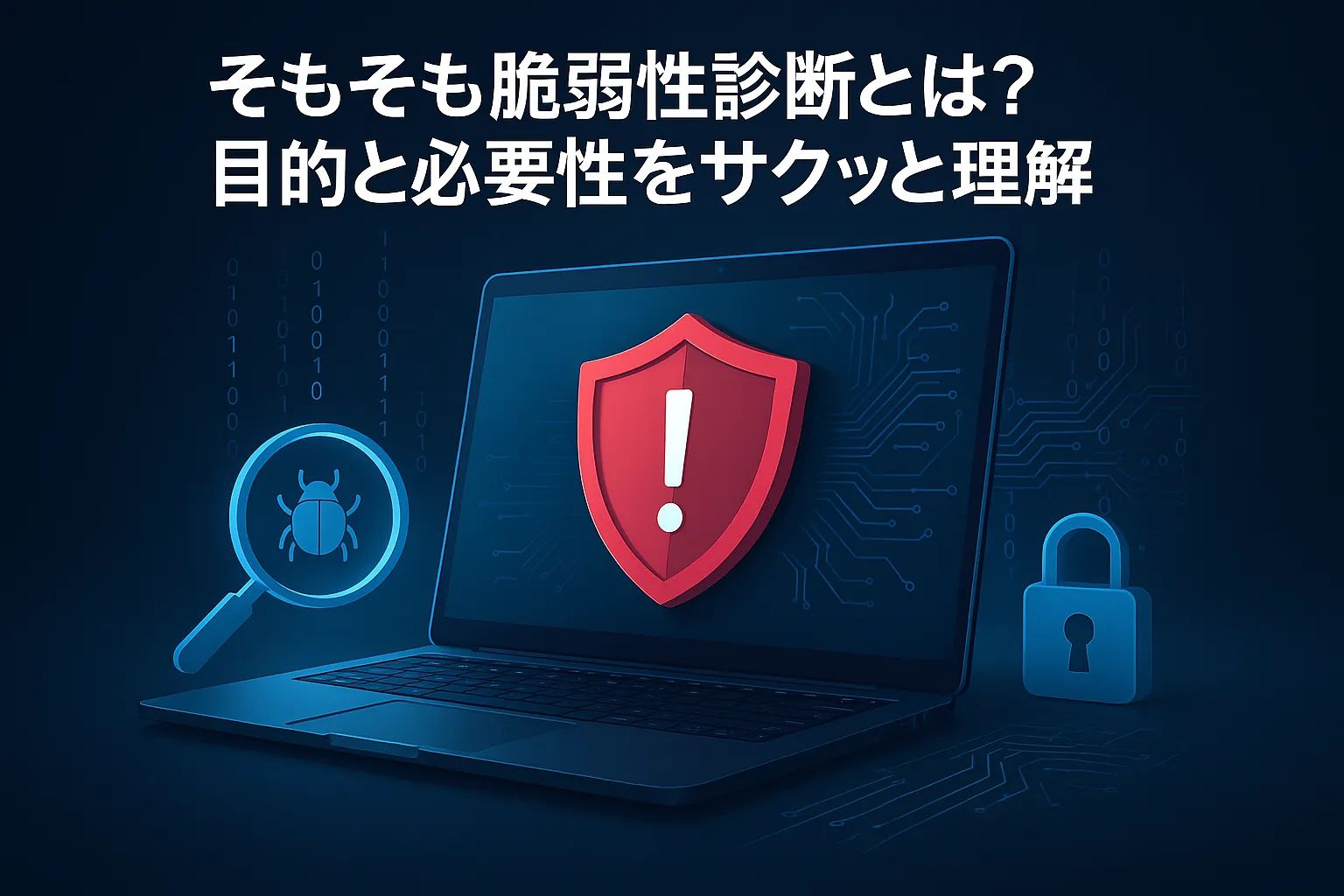
脆弱性診断とは、一言でいえば「Webサイトの健康診断」です。
Webサイトやそれを動かしているサーバーに、セキュリティ上の弱点(脆弱性)がないかを専門的な視点からチェックする作業を指します。
この診断の目的は、サイバー攻撃を受ける前に弱点を発見し、事前に対策を講じることです。
近年、企業の大小を問わずサイバー攻撃は増加しており、Webサイトの安全性を確保することは、ビジネスを継続する上で不可欠な要素となっています。
放置するリスク|情報漏洩やサイト改ざんは他人事ではない
もし脆弱性を放置してしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
決して他人事ではなく、あなたの会社にも起こりうる重大な問題に発展する可能性があります。
- 個人情報の漏洩
- 顧客情報や問い合わせフォームに入力された個人情報が盗まれ、企業の信用が失墜します。
- Webサイトの改ざん
- サイトの内容が書き換えられたり、ウイルスを仕込まれたりして、訪問者に被害が及ぶ可能性があります。
- 金銭的な被害
- ECサイトの場合、不正決済や偽の注文につながる恐れがあります。
- ビジネス機会の損失
- サイトが停止(サービス停止)に追い込まれ、売上やビジネスチャンスを失います。
これらのリスクを未然に防ぐためにも、定期的な脆弱性診断が重要なのです。
「ペネトレーションテスト」との違いは?
脆弱性診断とよく似た言葉に「ペネトレーションテスト(侵入テスト)」があります。
どちらもセキュリティを高めるための手法ですが、目的とやり方が異なります。
セキュリティ担当者でない場合は、まずは網羅的に弱点を探す「脆弱性診断」から始めるのが一般的です。
【初心者向け】脆弱性診断のやり方|信頼できる5ステップガイド
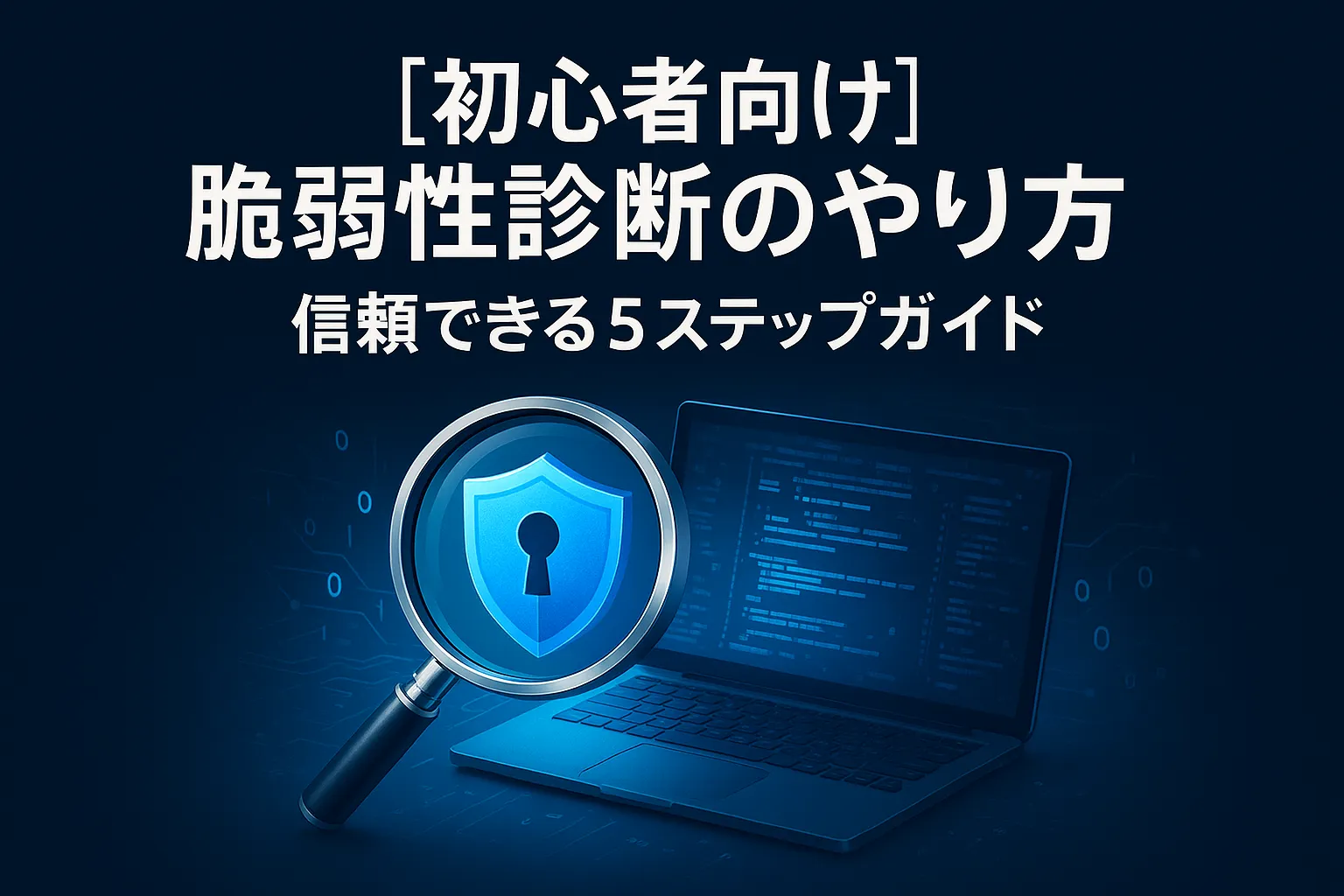
ここからは、この記事の核心である脆弱性診断の具体的なやり方を5つのステップで解説します。
この手順は、IPA(情報処理推進機構)などの公的機関が示すプロセスにも準拠しており、初心者の方でも安心して取り組める内容です。
各ステップで「何を」「なぜ」やるのかを理解しながら、一緒に進めていきましょう。
ステップ1:計画と範囲の決定|「何を」「どこまで」診断するか
診断を始める前に、まずは「何のために、どこを診断するのか」をはっきりさせましょう。
やみくもに始めても、時間と労力がかかるだけで効果は薄れてしまいます。
- 診断の目的を明確にする
- 「上司にサイトの安全性を報告するため」
- 「取引先からセキュリティ要件を求められているため」
- 「まずは自社のリスクを大まかに把握するため」
- 診断の対象範囲を決める
- 診断するWebサイトのURL(ドメイン)やIPアドレスを特定します。
- 複数のサイトを運営している場合は、どのサイトを対象にするか決めましょう。
- 優先順位をつける
- すべてを一度に診断するのが難しい場合は、特に重要なページから優先的に行います。
- 例えば、以下のようなページは優先度が高いと言えます。
- 個人情報を入力する「お問い合わせフォーム」
- ユーザーがログインする「ログインページ」
- 決済機能があるECサイトの「購入ページ」
この計画段階が、後のステップをスムーズに進めるための鍵となります。
ステップ2:情報収集|診断対象のサイトを調査する
次に、診断対象のWebサイトが「どのような部品でできているか」を調べます。
相手を知ることで、どのような診断が効果的かが見えてきます。
専門的なツールもありますが、ここではまず「何を調べるか」という概念を理解しましょう。
- OSの種類: Windows ServerやLinuxなど、サイトが動いているサーバーのOSは何か。
- Webサーバーの種類: ApacheやNginxなど、Webサイトのデータを送信しているソフトウェアは何か。
- 使用している言語・フレームワーク: PHP、Ruby、WordPressなど、サイトを構築している技術は何か。
これらの情報は、Webサイトのソースコードをブラウザで表示したり、「WhatWeb」のような簡単な調査ツールを使ったりすることで把握できる場合があります。
ステップ3:ツールで自動スCAN|無料で始められる方法
いよいよ本格的な診断です。
まずは自動診断ツールを使って、広く浅く、既知の脆弱性がないかをスキャンします。
ここでは、無料で利用できる高機能なツール「OWASP ZAP」を例に挙げます。
OWASP ZAPでの診断イメージ
- 公式サイトからOWASP ZAPをダウンロードし、PCにインストールします。
- 「自動スキャン」機能を選択し、診断したいWebサイトのURLを入力します。
- 「攻撃」ボタンをクリックすると、スキャンが開始されます。
- スキャンが完了すると、発見された脆弱性がリスクレベルごとに一覧で表示されます。
ツールを使うことで、効率的に多くの問題点を発見できますが、これが全てではないことを覚えておきましょう。
ステップ4:基本的な手動テスト|ツールが見つけられない穴を探す
ツールによる自動スキャンは万能ではありません。
特に、Webサイトの仕組み(ビジネスロジック)に依存するような複雑な脆弱性は見逃されがちです。
ここでは、初心者でも試せる基本的な手動テストを2つ紹介します。
これらのテストは、Webサイトがユーザーからの入力を適切に処理できているかを確認するものです。
もし上記のような反応があった場合は、専門家による詳細な調査が必要なサインかもしれません。
ステップ5:結果の分析と対策|見つかった問題をどう解決するか
診断で見つかった脆弱性を、どのように評価し、対策していくかを考えるステップです。
すべての問題を一度に解決するのは難しいため、優先順位を付けることが重要になります。
1. 深刻度を評価する
発見された脆弱性には、国際的な評価基準である「CVSS」というスコアが付けられることがよくあります。
このスコアを参考に、リスクの高さを判断します。
2. 対策の優先順位を決める
深刻度に加え、「その脆弱性がビジネスに与える影響の大きさ」も考慮して、対策の優先順位を決めます。
例えば、個人情報が漏洩するリスクのある脆弱性は、たとえスコアが中程度でも、優先的に対応すべきです。
診断して終わりではなく、この分析と対策のサイクルを回していくことが、サイトを安全に保つ上で最も大切です。
脆弱性診断に使えるツール|無料・有料の違いと選び方

自分で脆弱性診断を行うには、ツールの活用が不可欠です。
ツールには無料のものと有料のものがあり、それぞれに特徴があります。
自社の状況に合わせて適切なツールを選ぶためのポイントを解説します。
まずは無料ツールで診断の全体像を掴み、必要に応じて有料ツールや専門家への依頼を検討するのが賢明な進め方です。
まずはコレから!おすすめの無料診断ツール【OWASP ZAP】
これから脆弱性診断を始める方に、特におすすめしたいのが「OWASP ZAP」です。
- 世界標準の信頼性
- Webセキュリティの専門家団体「OWASP」が開発しており、信頼性が高いツールです。
- 無料で高機能
- 無料でありながら、自動スキャンから手動テストの支援まで幅広い機能を備えています。
- 豊富な日本語情報
- 世界中で使われているため、使い方を解説した日本語のWebサイトや書籍が多く、初心者でも学びやすい環境が整っています。
何から始めるか迷ったら、まずはOWASP ZAPをPCにインストールしてみることから始めましょう。
有料ツールや専門家への依頼を検討すべきタイミング
自己診断は有効な第一歩ですが、限界もあります。
以下のようなケースでは、有料ツールや外部の専門家による診断を検討することをおすすめします。
- ECサイトなど、クレジットカード情報を直接扱っている場合。
- 会員情報など、大量の個人情報を保持しているWebサイトの場合。
- PCI DSSなど、特定のセキュリティ基準への準拠が法的に求められる場合。
- 無料ツールで深刻な脆弱性が見つかったが、自社での原因特定や対策が難しい場合。
- 人的リソースが不足しており、診断に十分な時間を割けない場合。
自社のビジネスリスクを客観的に評価し、適切なレベルの診断を選択することが重要です。
【独自解説】守るだけじゃない!マーケティングも改善する「SpiderAF SiteScan」とは

脆弱性診断は、Webサイトを守るための「コスト」と捉えられがちです。
しかし、視点を変えれば、ビジネスの成果を向上させる「投資」にもなり得ます。
ここでは、セキュリティ対策とマーケティング成果の向上を両立する独自ソリューション「SpiderAF SiteScan」を紹介します。
このツールは、単に脆弱性を探すだけでなく、サイトのパフォーマンス改善にも貢献する点が大きな特徴です。
AIがセキュリティリスクを自動検知・管理|PCI DSS 4.0.1にも対応
SpiderAF SiteScanは、AIを活用してWebサイトに設置された外部スクリプトを常時監視します。
これにより、Formjacking(フォーム情報の窃取)のような巧妙な攻撃や、放置された古いプログラムの脆弱性を自動で検知します。
特に、2025年3月に完全施行されたカード情報保護の国際基準「PCI DSS 4.0.1」では、クライアントサイドのスクリプト管理が厳格に求められます。
SiteScanはこれらの要件に対応する機能を備えており、ECサイト運営者のコンプライアンス対応を強力に支援します。
Webサイトの表示速度やSEOも改善できる仕組み
Web担当者にとって、サイトの表示速度やSEO対策は重要な課題です。
SiteScanは、Webサイトに設置されているタグの動作を分析し、表示速度を低下させている不要なタグを特定します。
セキュリティを強化しながら、ユーザー体験(UX)やSEO評価の向上にもつながる、一石二鳥のソリューションと言えるでしょう。
初めての脆弱性診断で役立つ実践チェックリスト
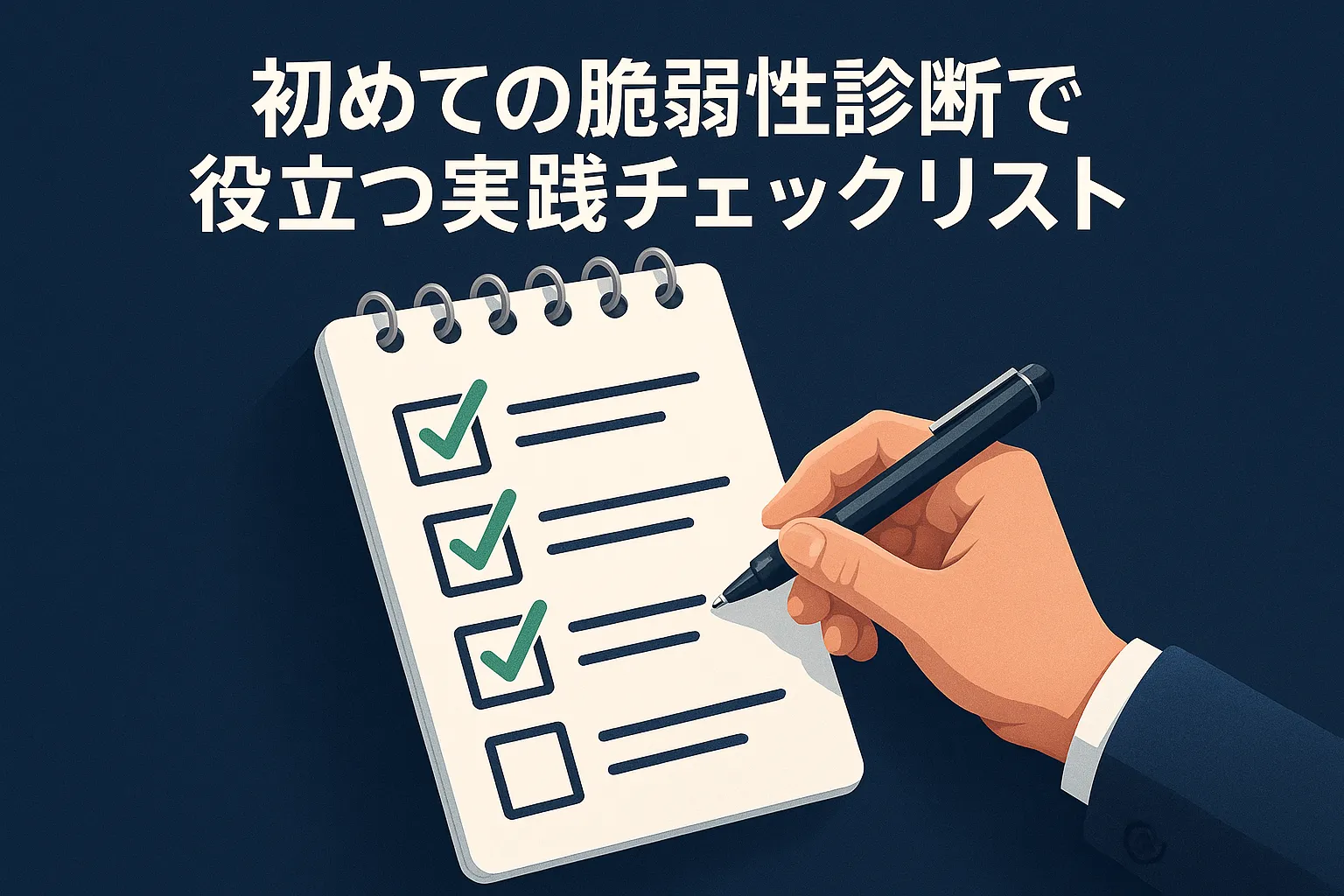
ここまで解説してきた内容を、実際に行動に移すためのチェックリストにまとめました。
初めての脆弱性診断をスムーズに進めるために、ぜひ活用してください。
【準備〜計画】フェーズ
- 診断の目的を明確にしたか(例:リスク把握、上司への報告)
- 診断対象のWebサイト(URL)を特定したか
- 優先的に診断するページ(例:ログインフォーム)を決めたか
- 関係者(上司、開発担当者など)に診断の実施を通知したか
【診断実施】フェーズ
- 無料の診断ツール(例:OWASP ZAP)をインストールしたか
- ツールで対象サイトの自動スキャンを実行したか
- 簡単な手動テスト(SQLインジェクション、XSSの確認)を試したか
【報告〜対策】フェーズ
- スキャン結果のレポートを確認したか
- 深刻度の高い脆弱性がないかを確認したか
- 診断結果と今後の対策案を上司に報告する準備はできたか
安心して診断を進めるための公的ガイドラインと資料
自己流で診断を進めることに不安を感じる場合は、公的機関が公開している信頼性の高いガイドラインを参考にしましょう。
これらの資料は、セキュリティ対策のよりどころとなります。
- IPA「安全なウェブサイトの作り方」
- Webサイトの脆弱性とその対策について、具体的な手口とコードレベルでの対策方法が非常に分かりやすくまとめられています。初心者必読の資料です。
- 経済産業省「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」
- 経営者の視点から、サイバーセキュリティ対策に取り組む際の考え方や体制づくりについて解説されています。上司への報告資料としても活用できます。
- JNSA「Webアプリケーション脆弱性診断ガイドライン」
- 診断の項目や手法について、より専門的に解説されています。診断の全体像を深く理解したい場合に役立ちます。
まとめ:脆弱性診断は自社のWebサイトを守る第一歩
本記事では、セキュリティ専門家でない方でも自分で脆弱性診断を始めるための具体的なやり方やツール、考え方について解説しました。
脆弱性診断は、一度実施して終わりではありません。
新しい脅威は日々生まれており、Webサイトの改修によって新たな脆弱性が生まれる可能性もあります。
まずはこの記事で紹介した5つのステップを参考に、自社のWebサイトの「健康診断」を実施してみてください。
それが、情報漏洩やサイト改ざんといった深刻なリスクからあなたの会社と顧客を守り、ビジネスを安心して継続していくための、最も重要で確実な第一歩となるはずです。





















